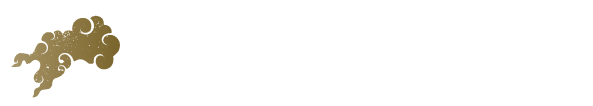【御詠歌】
煩悩を胸の智火にて八栗をば
修行者ならで誰か知るべき

本堂の横に建つ聖天堂には木喰以空上人が後水尾天皇皇后東福門院から賜った歓喜天が祀られています。商売繁盛や学業成就、縁結びにご利益があると言われ「八栗の聖天さん」として親しまれています。※画像1

本堂後方に建つ中将坊堂に祀られている中将坊は、さぬき三大天狗の一人。夜に山から下りてきて、民衆のために良いことをして朝帰る天狗。中将坊堂脇に下駄を奉納し翌日下駄が汚れていれば中将坊が働いてくれた印だとか。※画像2
八栗寺の歴史・由来
屋島の東、源平の古戦場を挟み標高375mの五剣山があります。地上から剣を突き上げたような神秘的な山です。八栗寺はその8合目にあり、多くの遍路さんはケーブルカーで登られます。 天長6年、大師がこの山に登り求聞寺法を修めた時に、五振りの剣が天振り注ぎ、山の鎮守蔵王権現が現れました。そして「この山は仏教相応の霊地なり」と告げられたので、大師はそれらの剣を山中に埋め鎮護とし大日如来像を刻み五剣山と名付けられました。
五剣山の頂上からは、讃岐、阿波、備前など四方八国が見渡すことができたので、もともと八国寺という寺名でした。 延暦年中、師は唐に留学する前に、再度この山に登りました。そして入唐求法の成否を占うために8個の焼き栗を植えられました。無事帰国し、再び訪れると、芽の出るはずない焼き栗が芽吹いていました。これが八国寺を八栗寺へ改名した由来です。この寺も長宗我部元親による八栗攻略の兵火により全焼しました。しかし、江戸時代に無辺上人が本堂(三間四面)、さらに高松藩主松平頼重が現在の本堂を再興、弘法大師作の聖観自在菩薩を本尊として安置し、観自在院と称するようになりました。五剣山は、宝永3年(1706)に、大地震を遭い、昔は五つの嶺のうち、東の一嶺が中腹より崩壊し、現在の姿になりました。
八栗寺の見どころ
聖天堂・中将坊堂・大師堂横の多宝塔・鐘楼堂(寛政3年(1791)建立。鐘楼堂に歌人で書家の會津八一(あいづやいち・秋草道人)の作歌揮毫の歌銘のある美術梵鐘があります。「わたつみの そこゆくうをの ひれにさへ ひひけこのかね のりのみために」)
八栗寺の年中行事
- 修正会(正月特別祈祷)
- 日時:元日〜7日迄
- 大般若法会(聖天尊正月大縁日)
- 日時:1月16日午後1時
- 花祭り(仏生会)
- 日時:4月8日
- 大般若法会(聖天尊春季大縁日)
- 日時:5月16日午後1時
- 青葉祭り(宗祖降誕会)
- 日時:6月15日
- 大般若法会(聖天尊秋季大縁日)
- 日時:旧暦9月16日午後1時
- 星供護摩(星祭り)
- 日時:冬至〜節分迄受付
- 聖天尊ご祈祷
- 日時:毎日受け付け
- 聖天尊護摩供養
- 日時:毎月15日及び月末午後7時
- 一日参り
- ※1.2.7.8.9月を除く・善哉接待
- 日時:1日10時〜
第85番 五剣山 観自在院 八栗寺
(ごけんざん かんじざいいん やくりじ)
- 宗派
- 真言宗大覚寺派
- 本尊
- 聖観世音菩薩
- 開基
- 弘法大師
- 創建
- 天長6年(829)
- 真言
- おん あろりきゃ そわか
アクセス情報
- 所在地
- 〒761-0121 香川県高松市牟礼町牟礼3416
- 電話
- 087-845-9603
- 駐車場
- あり(無料)
- 宿坊
- なし
- 公式HP
- http://yakuriji.jp/
志度インターチェンジから国道11号線を牟礼町へ。コトデン八栗駅前を左折して県道36号線を進み、標識のあるT字路を右折しケーブル登山口駅に着きます。
⇒ 現在地からのルート案内はこちら